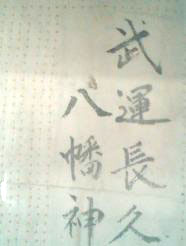資料 戻る
千人針は、出征兵士が無事に帰還できることを祈って多数の女性によって作られました。日中戦争開始とともに全国的に広まりま
した。日清・日露戦争の頃には、すでにハンカチほどの布に糸で結び目を作るという行為はおこなわれていたようで「千人結」と呼
ばれていました。
婦人会活動に取り入れられ、作り手は出征兵士の縁故者ばかりでなくなり、多数の千人針が作られ戦地へ送られるようになりまし
た。しかし、戦況が激しくなると、規制されたこともあり、あまり作られなくなりました。
千人針の起源はよくわかりませんが、無事に帰還して欲しいという願いを大勢の人の力に頼った合力祈願がはじまりで、これにさ
まざまな民間信仰が付随して発展したものと考えられています。
湊川神社(神戸市)は、祭神である楠正成が戦の神としての信仰を集めていて、戦勝を祈願したといいます。
信貴山寺(大阪府)の毘沙門天も戦の神として信仰を集め、毘沙門天のお使いが「虎」ということもあって、護符を千人針に縫い
つけて兵士に贈ることがありました。
寄せ書きした日章旗も「死線を越える」という思いを込めて兵士に贈ったといいます。これも大勢の力でもって無事生還を願った
もののひとつといえるでしょう。
出征兵士は戦地で、千人針や家族・親類から渡されたお守りなどを腹に巻いたり、帽子に縫いつけたりしました。
千人針を銃弾よけではなく、腹巻きとして使用していた人もありました。
千人針やお守りを付けていると「守られている」と心強く感じた人もあれば、シラミやノミの巣となった千人針を身につけるこ
とに抵抗を感じた人もありました。
千人針の布を梅酢につけて乾かすと、戦地で水が無くなったときや胃腸病で苦しんだときにかんで助かったこともあったそうで
す。
千人針に限らず日本人は、多数の人の力でもって目的を達成させる合力祈願をおこなってきました。例えば、雨乞い、風祭り、
虫送りなど一村各戸が参加すると祈願が達成されるようなもの。また、関東・東北地方では育ちの悪い子どもには、余り布を寄せ
集めて着物を縫い、これを着せることで子どもの安全を願うようなものがあります。
千人針を女性が作るという点では、沖縄の兄弟の旅立ちに際しては常にオナリ神(姉妹)が守っているという考え方、さらに兄
弟の旅立ちにはオナリ神の髪を守り袋に入れ、オナリ神が身に付けていた手ぬぐいを渡す習俗などが、千人針に通じるのではない
かと考えられています。沖縄では、千人針も妻ではなく姉妹が中心となり作っていたそうです。
千人針に刺す赤色の糸にも、厄年に赤いものを身につける、疱瘡除けに赤色を使用するなど、日本人の赤に対する思想が反映さ
れていると考えられています。
また、布に刺し込むという行為は、古来布を丈夫にする意味でしたが、背守りのように魔物が入らないように刺し込むこともあ
り、この行為にも呪術的な意味があるのではないかと考えられています。千人針を戦衣としての刺子の下着に連想した研究者もい
ました。
 |
「武運長久」「至誠一貫発光輝」の墨書があります。生地が赤く染まっているのは、赤糸の染料が汗でしみ出したのでしょうか。
(法量) 31.0×100.0(cm)
(結び目) 1019
(採集地) 高木西町
|
|
国防婦人会の製作で、「中夜久野村國防婦人會東支部」「純忠の光りは永遠ニ輝かん」「生きて平和の使たり死して護国の神となる」「正義ニ起たん日本魂」の墨書があります。赤糸で結ばれていないのが特色です。旧蔵者は、昭和13年に入隊しました。
(法量) 14.0×119.0(cm)
(結び目) 1012
(採集地) 一ヶ谷町
|
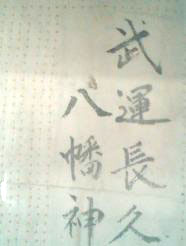 |
「武運長久 八幡神社」の墨書があります。硬貨が縫い付けられていた跡も見受けられます。赤糸で結ばれていないのが特色です。八幡神社は、勝負の神として崇敬を集めていました。市内では、月の初めに列を組んで西宮神社・広田神社に戦勝祈願に訪れる学校がありました。
(法量) 37.2×88.0(cm)
(結び目) 1005
(採集地) 甲子園六番町
|
 |
「義勇奉公ノ心」の文字になぞって結び目が作られています。金峯山寺蔵王堂(奈良県)をはじめ吉野山中の寺院の朱印が5ヶ所押されています。旧蔵者の母が弟の出征に際して贈ったもので、弟はビルマへ行き無事に戻ったそうです。戦地ではノミの巣となったそうです。
(法量) 17.0×190.0(cm)
(結び目) 1030
(採集地) 高塚町
|
 |
旧蔵者の父親が出征したときに持っていった千人針です。父親は2度出征し復員しましたが、あまり戦時中の話をしたがらなかったそうです。
(法量) 15.7×132.0(cm)
(結び目) 1000
(採集地) 瓦林町
|
 |
旧蔵者が夫の出征に際して作ったもので、お守りが縫い込んであります。「死線(4銭)を越える」「苦戦(9銭)を越える」という語呂合わせで5銭、10銭硬貨も付いています。夫は、太平洋戦争が始まってから出征しましたが、戦地にはいきませんでした。
(法量) 15.5×109(cm)
(結び目) 1000
(採集地) 甲子園一番町
|
西宮市 女性
自分で作ったことはないですが、出征する他人の為に結び目を一つ作りました。西宮市内の街頭で千人針をお願いしている人をみたことがあります。形は、お腹に巻くさらし布のようなものでした。
芦屋市 男性
町内隣組で持ち回り、母や姉妹が一針づつ赤い糸で目を作っていました。
身につけて出征しましたが、内地勤務のため軍隊生活では身につけずに終わりました。
日章旗に寄せ書きをして贈り、死線を越える事を祈りました。
神社の前では必ず脱帽礼拝しました。それが電車に乗っている時でも如何なる時でも直立し礼拝しました。
尼崎市 男性
千人針はみたことがありますが、身につけて出征したことはありません。
神戸市 男性
千人針は腹巻きとして使用していましたが、シラミの巣になり使用しなくなりました。
戦地へは、千人針以外にお守りを持っていきました。
神戸市 男性
毎日のように街頭に国防婦人会や女学生が並んで女性の通行人に千人針をお願いする姿を見ました。
信貴山(大阪府)の毘沙門天は戦の神で、必ず勝利するといわれ、又お使いの虎は千里を往き千里を還るという俚諺から参詣してお守りを千人針に縫いつけて兵士に贈ったりする人が多かったです。
千人針や身内・知人からのお守りを身につけ出征しました。それらに守られている気がました。
隣組で氏神さんや戦いの神として楠正成を祀る湊川神社に毎朝お詣りしました。
神戸市 男性
千人針を身につけ、50ヶ月に渡り転戦しました。千人針に銅貨・人髪の縫付が役に立ったようです。外地では寺社所在が稀ですが、機会に恵まれれば参拝しました。
神戸市 男性
(無事に帰れるように)只々武運長久を神社でお祈りするのみでした。
航空隊に入隊する者には千人針は考え及ばないことでした。
神戸市 女性
学校の先生から千人針の布を渡され3人で街頭に立ってお願いしました。「虎は強い。千里往って千里還る」という俚諺があって、寅年の女性にはお宅まで訪ねて年齢の数だけ針を入れて貰ったことがありました。
神戸市 女性
寅年生まれですが、千人針を縫って欲しいと家まで訪ねて来られたことはありません。街頭でお願いしている人がいたら、自分から進んで縫ってあげました。魚崎市場などでお願いしている人を見かけました。
夫は、昭和13年に千人針を持って出征しました。千人針は、姑が中心になって作りました。親が若ければ、妻よりも母親が作ることが多かった様な気がします。夫は、戦地で胸に銃弾を受けて帰国しました。血のついた日章旗(寄せ書きしたもの)は持ち帰ってきましたが、千人針はありませんでした。夫の部隊は全滅したので、その中で帰って来られたのは、千人針が守ってくれたのかもしれません。
神戸市 女性
赤い糸で一針づつ結び目を作りました。又、トラ年生まれの人は年の数だけ結び目を作れました。
神社に参拝して武運長久を祈りました。学校で、月に一度近くの神社に参拝しました。
飾磨郡 男性
神社のお守り札に無事帰還の祈願をしました。
千人針を持って出征しましたが、ノミやシラミの巣でした。
大阪市 男性
千人針を持って出征していませんが、身代わり不動のお守りを身につけていました。
大阪市 女性
千人針は、出征する兄のために作ったことがあります。母が千人針の布(腰に巻けるぐらいの長さ)を用意し、朱肉で1000個印を押してそれに一ずつ赤い糸で玉結びを作ってもらいました。千人針は、賑やかなところ、人通りの多いところ(新道の商店街か?)に一人で行って「お願いいたします」と声を掛けて玉結びをしてもらいました。寅年の人には、年の数だけしてもらえ、普通の人は一つだけでした。
女学校には近所の人の分を皆持ってきており、次々と千人針を刺していきました。
姉が寅年でしたが、家まで訪ねられたことはありませでした。千人針がはやっていたのは、昭和13〜15年の間で、みんな次々と出征して行ったため作られなくなりました。
千人針以外には、寄せ書きの旗をもって出征しました。寄せ書きは男性が行いました。「自分の代わりに戦ってきてくれ」といった文句が綴られていました。
大阪市 女性
街角で道行く女性に一針づつ縫って貰っている人をよくみかけました。とら年の人は年の数だけ縫えるとききました(虎は往って還るから)。五銭玉を縫い付けたものも見ました。死線を越えるそうです。千人針はシラミの巣になって困るらしいと聞きました。
神社のお守り袋で命が助かった話を聞いたような気がします。毎月8日に朝礼の後、学校生徒全員が裸足で神社に参拝しました。
県外(近畿) 男性
婦人会の方々が街頭に立って、通行する人々に一針縫うことをお願いしていました。
よく寺社に戦勝祈願に参っていました。学校、個人として友人・家族と共に参拝しました。
千人針は力強く感じて、軍務に励むことが出来たと親戚や村の人から聞いたことがあります。
千人針をよく見かけたのは、支那事変の頃で太平洋戦争が激しくなるとあまり見なくなりました。
東京都小石川区 男性
千人針をもって出征しました。内地では千人針を身に付けておりました。
名古屋市 女性
寄せ書きの日の丸の旗や神社のお守りで生還を祈りました。
千人針は、街頭で道行く人に頼んで何枚も作りました。
名古屋市 女性
路上でも毎日のように一針を求められました。寅年の女性は歳の数だけ刺せるといって貴重がられました。4銭(死線)を越えての意を込めて、5銭硬貨がよく用いられました。神社・仏閣の護符も用いられました。千人針を作って慰問袋に入れて戦地に送りました。
千人針を胴に巻いていて弾は当たりましたが、千人針が血染めになり助かった話を聞いたことがあります。
毎月8日(大詔奉戴日)には全校生徒列を作って護国神社などに参拝しました。
門司市(現北九州市) 女性
千人針は、女学校などに持参すると多くの人でさばけるので、殆ど毎日誰かが持参していた。
お守りや家族の写真が無事帰還や銃弾よけの願をこめる対象となったかもしれません。
1日と開戦の日は学校から全校生徒、近くのお宮に戦勝祈願に行きました。神社では大詔を校長先生が読まれていた気がします。時々、徒歩で一里以上ある招魂社にもお参りした記憶があります。
千人針で助かったと言う話は聞きませんでしたが、千人に守られていると軍人ご本人は信じたかもしれません。
身内に出征者がいないため、直接作ることはしませんでしたが、縫ってお手伝いはよくしました。筆の背で千の丸印をさらしにして赤糸で縫い込んでいきました。寅年生まれの人は年齢の数だけ縫う為重宝がられました。玉結びをしていたがシラミの巣になるらしく、後に半返し縫いにしました。
京城 女性
母が婦人会に入会しており、1日、15日に神社に参拝していました。
母は寅年だったので、結び目を年の数だけ作っていました。
兄たちが出征していたおり、母は毎朝陰膳を供えていました。
京城 女性
京城でも町角で白い布と赤い糸を持って横一列に並び、通行の女性に刺してもらいました。義弟のために私自身も作りました。義弟は銃弾を浴びましたが、帰還しました。
もどる
作成・2003年3月14日